 階段もできればない方がいいけれど、2階に上がるためにはエレベーターでもない限り絶対に必要になります。ですからできるだけ面積をとらない方法で作った方が他の部屋の床面積を増やせるためいいと思います。ただ廊下と同じでここも安全第一で考える必要があることは同じです。
階段もできればない方がいいけれど、2階に上がるためにはエレベーターでもない限り絶対に必要になります。ですからできるだけ面積をとらない方法で作った方が他の部屋の床面積を増やせるためいいと思います。ただ廊下と同じでここも安全第一で考える必要があることは同じです。
階段の形
階段の形にはまっすぐ、L字、コの字などがありますが、どれがいいのかと言われると、よくわからないというのが正直なところだと思います。L字やコの字は落ちた時に、中間に踊り場があるのでケガが少なくて済むからいいと言う人がいますが、弱点もあります。同じ角度であればまっすぐな階段のほうが面積が少なくて済むため、床面積が節約できます。また階段が曲がっているところで体を曲げないといけないため、その分労力が必要になります。どちらにするか人それぞれだと思いますが、まっすぐが優位なような気がします。
階段の幅
階段の幅は建築基準法の規定では75cm以上となっています。これを満たしていれば、それぞれの階段へのニーズでどうするか決めればいいと思います。総2階建てであれば頻繁に1階と2階を行き来するでしょう。それであれば最低でも94cmはあるといいようです。1mあれば十分すぎるほどですが、余裕があれば家のゆとりをかもしだす効果もあるのでいいかもしれません。中2階とか行き来があまりない場合は、75cm程度でもいいかもしれません。
階段の蹴上げと踏み面
建築基準法の規定では、階段の蹴上げ23cm以下、踏み面15cm以上となっています。まず踏み面は最低21cmくらいは必要です。人の足は女性で平均22~24cm、男性で平均25~27cmくらいが多いでしょう。階段を上がるときは、足を全部置かず、土踏まずより前の部分だけを使っています。また下りるときは、やや斜めに構え、指先より後ろの部分だけを乗せています。従って21cmあれば何とかいけるようです。もちろん踏み面を大きければ大きいほうが、楽なことは確かですが、大きくする分、家全体の面積が大きくなってしまい、建築費が高くなってしまいます。
蹴上げについては身長÷8を超えないようにします。身長÷9だと非常に楽になります。それ以下にした方が楽ですが、床面積が大きくなってしまい、坪単価が上がってしまいます。身長が違う場合、蹴上げは身長の低い人を基準にしましょう。あまり急ですと面積は小さくなり建築費は安くなるものの、転倒の恐れが高く危険です。階段で転倒すれば、決して軽傷で済むものではありません。なるべく安全で楽な角度の階段にするべきです。ちなみに階段の勾配は、人間の歩幅から割り出した寸法が良いそうです。最も適当な傾斜は30~35度でのようです。
階段の手すり
 手すり棒については、既製品の場合、直径3.3cm前後のものと、4.4cm前後のものがあります。太いほうが丈夫そうに感じますが、必ず細い方にしましょう。理由は、太い手すりだと、指の入る隙間が狭いので、指の甲を壁にすって、怪我をしやすくなるからです。また取り付ける高さは、体重を乗せることができる高さがいいとのことです。低すぎると腰を曲げることになるので、体重が乗せられません。上るときは手すりの高さが低くても、握るところはある程度の高さになりますが、下りるときは腰を曲げることになり、低すぎてとても危なくなります。高さの目安は、骨盤あるいは手首の高さです。このあたりだと、腰を曲げずに体重を乗せることができます。背が違う場合は、高い人に合わせましょう。低い場合は体重は乗せにくいですが、高い分には乗せられるからです。小さな子供がいる家庭の場合は、子供専用の手すりを付けると便利です。高さは大人用の半分くらいの高さでよいかと思います。
手すり棒については、既製品の場合、直径3.3cm前後のものと、4.4cm前後のものがあります。太いほうが丈夫そうに感じますが、必ず細い方にしましょう。理由は、太い手すりだと、指の入る隙間が狭いので、指の甲を壁にすって、怪我をしやすくなるからです。また取り付ける高さは、体重を乗せることができる高さがいいとのことです。低すぎると腰を曲げることになるので、体重が乗せられません。上るときは手すりの高さが低くても、握るところはある程度の高さになりますが、下りるときは腰を曲げることになり、低すぎてとても危なくなります。高さの目安は、骨盤あるいは手首の高さです。このあたりだと、腰を曲げずに体重を乗せることができます。背が違う場合は、高い人に合わせましょう。低い場合は体重は乗せにくいですが、高い分には乗せられるからです。小さな子供がいる家庭の場合は、子供専用の手すりを付けると便利です。高さは大人用の半分くらいの高さでよいかと思います。
階段の滑り止め
階段の形がどうあれ、重要なことは転倒しないように対策することです。一番大切なことは角度をゆるくつくることです。そして必ず滑り止めを付けましょう。ホームセンターに行けば、階段の縁に貼る滑り止めステップや、足が滑らず防音効果もある滑り止めマットを売っています。
階段のまとめ
階段は安全第一です。そのために形、幅、蹴上げ、踏み面、手すり、滑り止めをよく考えましょう。具体的には形はまっすぐ、幅は94cm以上、蹴上げは身長÷8以下、踏み面は21cm以上、手すりは骨盤あるいは手首の高さで子供用もあると便利です。滑り止めを忘れずにつけましょう。
参考:成美堂出版 安らぐ家は「間取り」で決まる
ホール 他の記事
- 玄関は引き戸がいい!開けたままできるメリット大、バリアフリーも!
- 玄関のポイント!土間断熱、コート収納、照明の位置と人感センサー!
- 玄関土間のタイルは原田左官工業のスーパーメガテクノタイルがいい!
- 玄関に高い収納、等身大の鏡付!すのことレインコート掛け、傘立て!
- 玄関のバリアフリーはスロープ、手すり、引き戸、安全な土間づくり!
- 廊下は安全な幅と床、照明は人感センサー、バリアフリーも考えて!
家づくりの目次はこちら
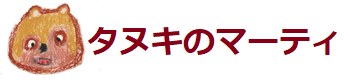
 子供の安全に意識の高い父母の方々に人気があり、選ばれ続けている安心安全な食品・日用品を紹介します。→
子供の安全に意識の高い父母の方々に人気があり、選ばれ続けている安心安全な食品・日用品を紹介します。→